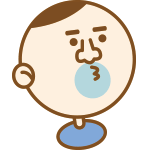
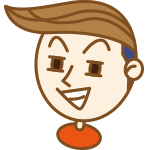
また車両保険も、どんなときに必要なのか考えてみるっス!
愛車がキズついたとき、車両保険を使って修理するか、それとも自己負担にするか迷ったことありませんか?
そもそも車両保険といえば、あなたが設定した補償金額を上限として、修理費用などを補償してくれる便利な保険ですが、この補償料を受け取るときに注意すべきことがあります。
それは、車両保険を使うと等級がダウンし、翌年以降の保険料が上がってしまうこと💰
つまり、”保険料が上がってでも補償料を受け取った方がいいのか”を見極める必要があります!
ただ、初めにマルクが言ったとおり、等級の割引率・事故後の等級ダウン・免責額などが絡んでくるので、どちらがいいのかを判断するのが悩みどころ…。
そこで今回は、車の修理に車両保険を使うべきかの判断基準、そして自腹で修理する場合の注意点などをご紹介します!
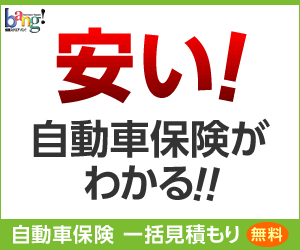
車の修理に車両保険を使うべきかを判断する3つのポイント

車両保険を使うべきかの判断をするためには、まずノンフリート等級の仕組みについて理解しておく必要があります🚗
事故歴に応じた保険料の割引・割増を適用する制度のことで、1~20等級の20段階に区分されています。
初めて契約する場合は6等級からの開始となり、セカンドカー特約などの契約条件によっては7等級から開始の場合もあります。
また、免責金額の設定によってもトータルの支払額が変わってくるので、次からそれぞれ詳しくご紹介します。
1、ノンフリート等級の係数によって保険料の割引率が変わる

ノンフリート等級が、1〜20等級までの区分に分けられていることはほとんどの方がご存知だと思いますが、その区分の中でさらに”無事故”と”事故有”の2つの係数に別けられていたことはご存知でしたか?
実は、2013年10月以降に車両保険の新規契約もしくは更新する場合、前年に保険金を受け取っていたら、翌年度から事故有係数という割高な保険料になる新等級制度に切り替わっていたんです🚙
事故で保険金を受け取ると等級が下がるだけでなく、さらに割引率の低い事故有係数になってしまい、しかも場合によっては翌年から3年間それが続いてしまうという…。

ただその後3年間、無事故であれば無事故係数に復活し、一般的な割引率へと適用されます。
じゃあ、どのくらい事故無・事故有の係数で割引率が変わるのか、下の表で確認してみましょう!
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 無事故係数 | +64% | +28% | +12% | 2% | 13% |
| 事故有係数 | |||||
| 等級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 無事故係数 | 19% | 30% | 40% | 43% | 45% |
| 事故有係数 | 20% | 21% | 22% | 23% | |
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 無事故係数 | 47% | 47% | 48% | 49% | 50% |
| 事故有係数 | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% |
| 等級 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 無事故係数 | 51% | 52% | 53% | 54% | 64% |
| 事故有係数 | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
※SBI損保/等級毎の割増引率

つまり、保険加入したばかりの6等級(19%)の割引率とほぼ変わらないので、結構イタイ出費っスよね。
2、事故有係数の等級ダウンを見据えて年間保険料がいくらか算出

では、前段で紹介した等級表をもとに、具体的な保険料のシミュレーションをしてみましょう🔎
仮にアナタが10等級で、年間保険料は割引き無しのピッタリ100,000円だったとします。
等級表と照らし合わせると、無事故係数であれば10等級の割引率は45%受けられることになり、保険料は55,000円と算出することができます💰
翌年以降も無事故のままであれば、11等級(47%)・12等級(47%)・13等級(48%)と上がっていくので、保険料も53,000円・53,000円・52,000円と安くなり、3年間での合計保険料は157,000円になります。
でも、3等級ダウンの事故を起こしてしまうと翌年は7等級に下がり、しかも事故有係数の割引率が適用されてしまうので20%となって、保険料は80,000円に…。
また、2年目・3年目も8等級(21%)・9等級(22%)の事故有係数になるので、保険料は79,000円、78,000円となり、事故後3年間の保険料合計額は237,000円と算出することができます。
つまり事故無と事故有で比較すると、その差は80,000円となって、しかも等級数は4つも差がついてしまうとに😥
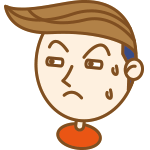
3、車両保険に加入している場合の免責額をチェック

車両保険に加入している場合、免責の設定をしていることになります。
そもそも免責とは、アナタが保険金を受け取る場合に自己負担する設定金額のこと!
もし契約内容に”免責5-10”と記載されていたとしたら、1回目の負担額が5万円、2回目以降の負担額が10万円に設定していると判断できます。
例えば、免責金額が5万円に設定されていて車の修理に8万円かかるとしたら、保険会社から保険金が支払われる金額は3万円だけになるということです💰
仮に修理代が50万円など高額になった場合は、免責が5万円でも45万円の保険金が受け取れるので、車両保険を使うべきと言えますね!
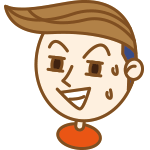
車両保険はどんな人に必要?

前段で例を挙げたとおり、修理代に対して免責設定額の自己負担・等級ダウン・割引率などを総合的に考えると、車両保険に加入する必要性ってあまりないんじゃないかと思ったのではないでしょうか?
そこでポイントになってくるのが、アナタが事故を起こすリスクの度合い・事故を起こしてしまったときにいくらまで修理代を負担できるのか・車両保険に入る価値のある車なのかという3つ💰
事故を起こすリスクの度合いをはかるのは、感覚的な要素が大きいので判断が難しいと思いますが、例えば週末ドライバー・セカンドカーなどの使用頻度が低い方や、ある程度は自分で修理ができるといった方であれば、車を修理に出す可能性は低くなると想定できます🚗
また、自分の貯金から約15〜100万円の修理費用まで対処できるのであれば、車両保険に入らなくてもいいと判断できます!
逆に修理代を用意することが難しく、さらには車が長期間使えなくなると生活や仕事などに支障が出るのなら、車両保険には入っておいたほうが良いと言えますよね。
あと、メルセデスベンツ・BMW・アウディーなどの輸入車に乗っている方も、国産車と比較するとコンピュータの故障頻度や純正パーツや工賃などが高いことから、加入しておくことをオススメします!
そして最後にもう一つの考え方として、車両保険をかけるべき車なのかを見極めること🚙
新車であれば車両価値も高く、万が一の損害に備えることは重要だと思いますが、もしアナタが乗っている車が年式10年・10万㎞を超えているようなモノであれば、中古車市場価値はほとんど無いと言えるので車両保険をかけない方が賢い選択かもしれません💡
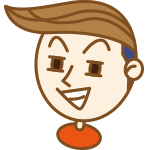
ちなみに2015年の保険スクエアbang!利用者データによると、車両保険の加入割合は全体の56.4%で平均保険金額は約150万円っス!
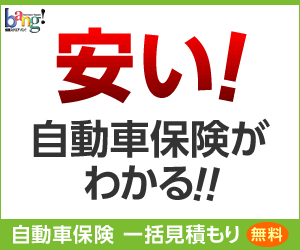
車を修理に出す前に知っておきたい2つの方法

車が破損し、保険会社に相談して言われるがままに車を修理してしまうと損をする可能性があるので、中古パーツを使って修理費を抑えたり保険金の受け取り方など、知っているだけでアナタが得をするかもしれない方法もご紹介します💡
1、中古パーツを使って修理代を抑える

等級ダウンや免責などを考慮した場合、修理代が15万円以下であれば車両保険を使わずに自腹で修理することが、一つのボーダーラインとご紹介しました📢
実際にいくらで修理できるのかはカスタムショップや板金塗装工場から見積もりを貰わないとわかりませんが、見積もりを取る際に「どうにか15万円以下で修理できないですか?」と相談してみましょう💡
ディーラーで修理の依頼をすると、ほぼ値引きなどの相談は難しいですが、街のショップでは柔軟に対応してくれるところも多く、私が相談した時は中古パーツなどを取り寄せてくれコストダウンしてくれました!
また今では、Yahoo!オークションやメルカリなどを使えば、自分で必要な中古パーツを取り寄せることも可能なので、インターネットもぜひ活用してみましょう💻
2、修理せずに保険金を振り込みにしてもらう

車両保険で支払われる保険金は、事故車両の修理以外で使ってはいけないなんて決まりはありません。
意外に思われるかもしれませんが、保険金は何に使ってもアナタの自由💰
通常は車の修理代が保険会社から修理工場に支払われることになりますが、保険会社と修理工場へ修理しない旨を伝えれば、アナタの指定した口座に振り込んでもらうのもOK!
もし、車検が切れるタイミングで廃車にする予定だった車の場合、事故を起こしてしまったときに修理をせず、保険会社から送金された保険金を新しい車にあてるのはむしろ普通の考え方ですよね?
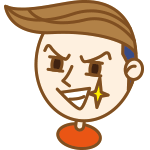
また廃車にしない場合でも、サイドミラーの擦りキズやドアノブのキズなど、そのまま放っておいても走行に問題ないような車検に通るキズであれば、保険金をもらって修理しないことも可能ですよ🚙
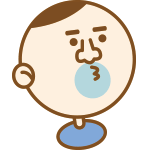
車の修理代を請求する目安金額まとめ
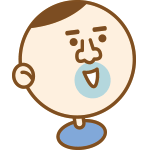
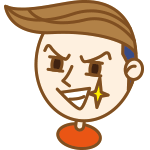
ちなみに自損事故ではなく相手がいる事故にあった場合、相手の自動車保険で修理できるとしたときに、さらに自分の車両保険からも保険金をもらうことはできません!
またその際は、警察に届けて事故証明を発行してもらわないと、保険会社は対応できないので注意しておきましょう!

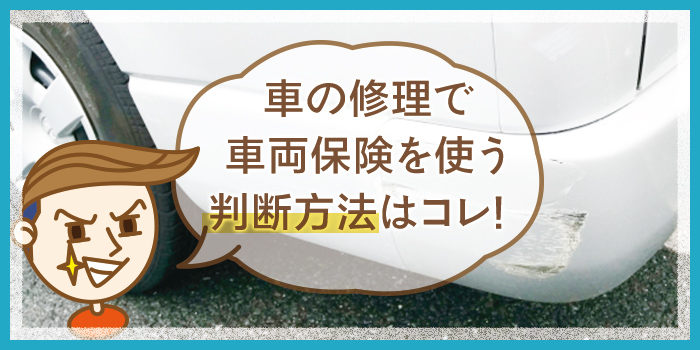
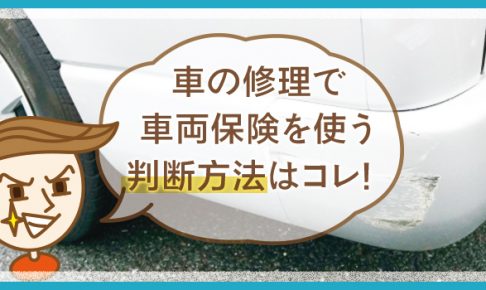
 私はココの中古車一括査定比較サービスを使うことで、最初に提示された最安査定額より、30万以上愛車を高く売ることができ、ボーナスに近い臨時収入を得ることができました!
私はココの中古車一括査定比較サービスを使うことで、最初に提示された最安査定額より、30万以上愛車を高く売ることができ、ボーナスに近い臨時収入を得ることができました! 
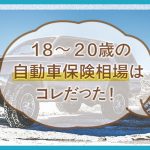
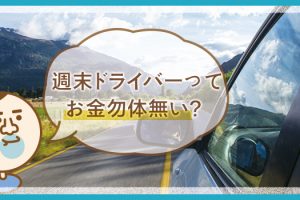
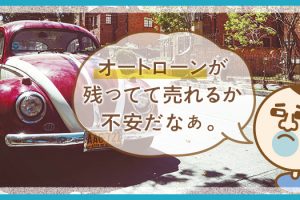
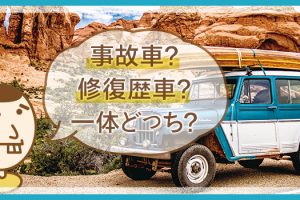
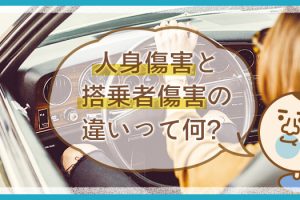


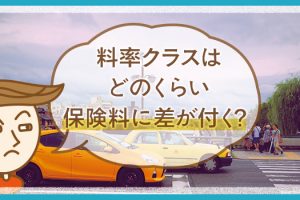
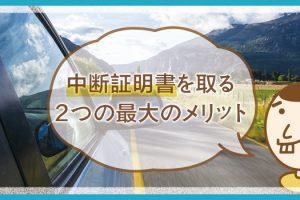







あと損するくらいなら、車両保険に入らん方がいいんやないと?